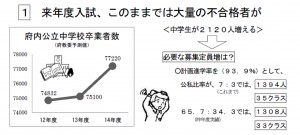今こそ
人間を大切にする教育・社会の実現を
「いじめ」問題の克服へ
大津市の中学生「いじめ」自殺事件など、「いじめ」と自殺が大きな社会問題となっています。また日本の自殺者は14年連続で年間3万人を超え、1日に80人以上が自殺に追い込まれるという異常な社会となっています。とくに15~34歳では死因の第1位が自殺です。「いじめ」と自殺の克服へ、いま教育と社会に何が求められているのでしょうか。
人間の尊厳と命が問われている
いま人間らしく生きることの尊さが問われています。自殺者が年間3万人を超えた98年は、弱肉強食の新自由主義「構造改革」が一気に強められた時でした。カネとモノを最も大切にし、人をモノとして扱う派遣労働など、人を人として大切にしない社会風潮を広げました。
そして弱い者いじめを是認し、「効率」「成果」で人間が評価され、人間らしい労働や人間らしく生きるための最低限の社会保障まで踏みにじり、新たな貧困と格差が拡大させられています。
「いじめ」問題には、こうした重大な社会的背景があります。しかし今、大震災と原発事故に直面し、多くの国民が生命の尊さ、人間らしく生きることの尊さを見つめ直しています。「いじめ」自殺事件も、人間の尊厳と命の大切さを問うものであり、一体の課題としてとらえることが重要です。
「いじめ」克服への中心問題深刻な「いじめ」が起きる根本原因
深刻な「いじめ」問題の根本原因には、子どもを追い立て、追いつめ、ストレスを増幅させている「競争と管理」、選別と切りすての教育政策があります。子どもたちは常に比較され、ほめられたり評価されたりすることが少なく、自分が生きていることの意味や値うちが実感できず、人格を傷つけられ、全体としてひどい「いじめ」の状況に追い込まれています。
さらに子どもを人間としてではなく「人材」として扱い、教育の目的を子どもの人間的な成長・発達よりも、大企業に役立つ人材育成に変質化させる動きが強められています。
「いじめ」克服へ、こうした人間を大切にしない教育政策の抜本的な転換をめざすとともに、1人ひとりの子どもが、本当に人間として大切にされる教育になっているのか、常に自己点検していくことが重要です。
問題が隠蔽される理由
「いじめ」は、いつ、どこで起きても、おかしくない問題であり、早期の発見と機敏な対応がカギとなります。そしてきちんとした事実関係と実態の把握が、きわめて重要になりますが、教員評価・学校評価が強められる下で、「いい学校に見せたい」「いいクラスに見せたい」「問題がないように見せたい」と外見をつくろう方向に大きな圧力がかっています。
「いじめ」発生件数の数値目標化はその典型です。限りなくゼロに近い方がよいとされ、実態を覆い隠す隠蔽体質の温床となっています。また失敗なしに子どもの成長・発達はありえないにもかかわらず、評価システムは失敗を許さない体制づくりとなっており、子どもと正面から向き合う教育を困難にしています。
こうした政策は、抜本的に見直さなければなりません。
いじめ克服の方向
―豊富な実践と経験―
① 子どもたちの自主性と自治の力を育む、子どもが主人公の学校づくりをすすめ、「いじめ」を生み出さない、前向きな集団の流れをクラスや学年につくり出していくことが重要です。そして特に「いじめ」は子どもの内面と深くかかわる問題であり、子どもたちの本音が通い合わせられる教育をすすめていくことです。そして日々の実践の中で、人間関係づくりの「へたさ」や「もつれ」を克服しながら、暴言や暴力を許さない集団の民主的な関係づくりをすすめ、いじめの構造(見て見ぬふり、あきらめ、加担)へ、発展させないようとりくむことです。
② いじめ問題の克服を困難にする大きな要因に多すぎる学級定員や、教職員不足など劣悪な教育条件があります。教職員が子どもたちとじっくり向き合い、保護者と力を合わせて課題に立ち向かうためには、30人学級実現、教職員の長時間労働解消などが急務です。
人間の尊厳をかけるたたかいが、全国で発展
原発再稼働に反対する国会前の行動は、爆発的に増加し、これまで政治や社会運動とは全く無縁だった人たちが、自発的に「国民の声を聞け」と立ち上がりはじめています。さらにオスプレイ配備反対や消費税増税反対、TPP反対などでも運動が大きく広がり始めています。これらの根源には「人間の命と尊厳を守れ」という強い願いがあります。
これはとても重要な変化です。「いじめ」の社会的背景となっている、人を人として大切にしない新自由主義「構造改革」に反対する国民の立ち上がりです。そしてこの立ち上がりには「人間の命と尊厳を守る」人間的な連帯と助け合いがあります。こうした社会的連帯を強めていくことが、「いじめ」を生み出す社会風潮の克服にもつながります。「いじめ」克服へ学校・地域から人間の尊厳をまもる共同を大きく広げていきましょう。
府の「2条例」は「いじめ」問題をいっそう深刻化させる
「格差拡大はダメ、競争はダメ、このような甘い言葉こそ危険」(橋下市長)
一、1人ひとりの子どもの成長・発達を自己責任に追い込み、大事にしない。
二、「格差はあっていい、秀でた者を育てていく」と格差を是認し、切りすての競争教育おしつけで「勝ち組・負け組」をつくり出す。
利己主義で勝ち抜く子どもを求め、人を思いやる心、やさしい心を失わせる。
三、「数値目標」押しつけで、「目的のためには手段を選ぶな、結果を出せ」と、1人ひとりの子どもの尊厳と価値を見失なわせる。
四、「教育は2万%強制」と命令と強制で教育をすすめ、子どもの失敗や思春期の困難さを許さず、冷たい管理へ。脅しは「いじめ」を陰湿化させるだけ。
五、子ども、教職員、父母のストレスを、いっそう強める。